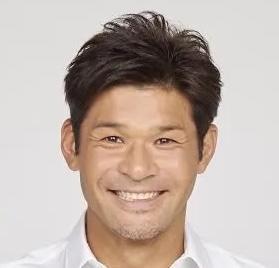正直、ギャルに憧れた人、多くないですか?
明るい髪色にバサバサのつけまつげ、キラキラの派手ネイル。
ギャルは「ギャル」という独自のカルチャーを創り出し、いつだって周囲の目を引く存在でした。
男ウケでも女ウケでもない「自分ウケ」を徹底するその強さは、見た目だけに留まらず、枠にとらわれない考え方や常識をぶち壊すような言動にも表れていました。正直、私はギャルの“自分自身のマインドを貫く姿勢“には心底憧れました。
浜崎あゆみの「evolution」って曲を知ってますか?あの曲、ただのブチ上げソングじゃないんですよ。
「現実は裏切るもので 判断さえ誤るからね そこにある価値は その目でちゃんと見極めていてね 自分のものさしで」
とか、
「そうだね僕達新しい時代を 迎えたみたいで奇跡的かもね 二度とはちょっと味わえないかもね もう一度 思い出して」
とか、自分自身で決めていくことの大切さとこの時代に生まれたことへの奇跡が詰まりに詰まった一曲なんです!!!あぁ、これほど最強になれる曲は他にない、と震えたのを今でも鮮明に覚えてます。
普通なんてつまらない!
90年代から現在に至るまで、いつでもギャルは注目される存在。メイクやファッションから伝わる「普通なんてつまらない」というマインドは、自分らしさに悩む思春期の女子にとってまぶしいほどの憧れです。
メイクの仕方だってそう。全員のギャルが同じメイク方法ではなく、自分の顔が盛れるなら、アイラインが目の幅を大きく超えたって、複数のつけまつ毛を切ったりカスタムしたっていい。理由は一つ、盛れるから!
他人がどう思うかよりも「自分のテンションが上がるか」「自分がかわいいと思うか」にフォーカスし、それがどんなに派手だろうと、周りから否定されても関係ない。その「私は私」という意思は、確実に周囲にも影響を与えたことでしょう。
常識を打ち破る反骨精神
「目上の人には礼儀正しく、高校生にメイクは不必要」
そんな常識は彼女たちにとって何の意味もありません。大人が常識論をぶつけたところで、「一般常識って誰が決めたの?」「誰がどんなメイクしたっていいじゃん!」と軽くあしらわれてしまうでしょう。
ギャルが持つ世の中への反骨精神は「自分らしくいることが最強」というマインドから生まれたもの。どんな状況・環境であれ、誰もが「自分らしくありたい」と心から思っているからこそ、ギャルというジャンルがメインカルチャーから浮くことなく、受け入れられてきたのかもしれませんね。
サブカルチャーなのに「陽」!

サブカルチャーはメインカルチャーの一段下と考えられることが一般的で、どちらかというと「陰」のイメージ。ギャル文化もメインカルチャーの下に位置しているはずですが、ギャルの持つ明るいキャラクターから、なぜか圧倒的な「陽」のイメージを受けます。
学校にギャルが一人いるだけで、なぜか周囲の雰囲気が明るく感じる。ギャルが道を歩くだけで、謎のスター感がある。ギャルが隣にいるだけで、なんか強くなった気がする。話しかけられたらなんか嬉しい…!ギャルに大丈夫って言われたら、本当になんとかなる気がするし、むしろなんでもできちゃう気がしたのは私だけでしょうか。
ギャルはサブカルチャー的な存在でありながら、常にリア充グループに属していました。それが、ほかのサブカルチャーでは出せない「陽」のイメージなのでしょう。
むしろメインカルチャーをけん引してしまった感
1990年代の茶髪やミニスカート、細眉などのギャル文化は、元々はギャルだけのものだったはず。しかし、そこから時代とともにギャルの種類が変化していき、いつしかメインカルチャー、つまり一般人のメイクやファッション、生き方にも部分的に取り入れられるようになりました。
ギャルの持つ圧倒的なパワーは、周囲への影響力も非常に大きなものでした。
ギャルが持つ自分らしさを突き詰めるストイックさや、「盛る」ためなら手段を選ばない開拓心などの莫大なエネルギーがメインカルチャーをけん引した理由といえます。
勇気がなくてギャルになれなかった人も
とはいえ、今日から突然ギャルになれるわけでもないのが現実。普通の女子がギャルのヘアメイクに挑戦することは非常に勇気のいることでした。現に、私が思春期の頃は「前髪を切っただけで恥ずかしくなってしまうのに、髪を明るく染めるなんて…!」と思っていましたから…。
それに、ギャルは強く、確固たる「自分」を持っている存在。「自分!」というマインドを根拠なく、いきなり持つことなどなかなか難しいですよね。
でも一つ言えるのは、ギャルは成り下がるのではなく、成り上がっていくイメージ。
まるで一段上のステージに自ら上がっていくような…。もしかしたら、ギャルは最初からギャルだったわけではなく、自らギャルというステージに上がっていったのかも。
ギャルを批判するのは無粋だという雰囲気=無敵感
ギャルは若者文化であり、若者の代弁者。平成時代は“ギャルを批判する大人は若者に理解がない無粋な人”というような風潮もあったほど。
テレビ番組では、社会問題や事件に対するギャルのぶっとんだコメントに対して、出演者一同がまず驚く。そして突っ込みが入る。でも出演者の中でも年配の芸能人や、インテリコメンテーターがギャルの意見にのっかるという場面も多く見られました。ほかにも、ニュースキャスターや学者まで多くの人がギャルへの理解を示しました。
ギャルが一つ発言すると周囲が率先して耳を貸し、他にはない斬新な意見やアイデアに大人の目が輝く。ユニークな発言に思わずクスっと笑ってしまう雰囲気が生まれて、なぜか力が入っていた肩の荷がスッと軽くなる。
みんなのムードメーカー的存在としても、若者の代弁者としても、ギャルはかっこよくて無敵でした。
ヤマンバギャルって歌舞伎っぽい気がする

いきなり「歌舞伎」というワードが出てきてびっくりした人もいるかもしれません。実は筆者は初めてヤマンバギャルを見たとき、「歌舞伎っぽいな」と感じていたのです。鼻に太く入れたハイライト、鮮やかなブルーやピンクのアイシャドウ、本来の目の形を大きく変える囲みアイライン、そのどれもが歌舞伎の隈取に似ていると。
メイクだけでなく、カラフルで派手なファッションや、明るいヘアカラー、盛り系ヘアスタイルもどことなく歌舞伎の装いに近い。
そのほか、ギャルに対する謎の憧れを掘り下げれば掘り下げるほど、やっぱりギャルは歌舞伎っぽい!と気づいたのです。
奇抜で人目をひくビジュアル
歌舞伎の始まりとなった「かぶき者」。色とりどりの派手な着物を身につけ、「茶筅髪」という斬新な髪型をしていました。
茶筅髪というのは、頭のてっぺんで髪を一旦結んでから、その先端を茶筅(お茶を点てるときに使うマドラーのような道具)のようにアレンジするヘアスタイルです。これはビジュアル上、ギャルといえるのではないでしょうか。
派手な着物はギャル服、茶筅髪は奇抜な髪型。当時ヘアカラー剤があったなら、きっとかぶき者たちは輝くように明るい茶髪にしていたに違いありません。
しかし、当時のかぶき者は男性が中心で、男性が色鮮やかな女物の着物をマントのように羽織っていたといわれています。中にはビロード製の襟を愛用したり、動物の毛皮を着物にはぎ合わせた人もいたとか。
このことから言えるのは、多くのかぶき者が「自分の美的センス」や「自身の個性」を心底大切にしていたということ。あれ、なんだか生き方や考え方もギャルっぽくないですか?
背景には不安な社会情勢
ギャルがブームになったのはバブル崩壊後の90年代半ば。バブル全盛期にディスコで踊っていた、肩パットやタイトスカートなどのコンサバ系スーツのお姉さんとは打って変わり、ポップで露出の高いファッション、ガングロ、茶髪のギャルが台頭したのです。
それでは歌舞伎はどうでしょう。歌舞伎の語源は、“派手な身なりで、常識を外れた行動に走る「かぶき者」から来ています。彼らも戦国時代の明日も分からぬ社会の中に生きていました。
人は強い社会不安の中にいると、社会=常識を打ち破ってみたくなるのかもしれません。
かぶき踊り=パラパラ?
安土桃山時代には、女性芸能者である出雲阿国が登場します。出雲阿国は「かぶき踊り」を創始し、京都にて名を馳せます。かぶき踊りは、女性である阿国が上述したような男性のかぶき者の格好をして踊るという内容で、当時はセンセーショナルなものでした。その後かぶき踊りは大流行し、全国に広がっていきます。
このようにかぶき踊りが流行した背景には「風流(ふりゅう)踊り」の爆発的な人気もあります。風流踊りはさまざまな扮装をした人々が集まり、当時の流行歌にあわせて皆で踊るというものでした。この風流踊りが、かぶき踊りの母体となったといわれています。また、この風流踊りは当時の盆踊りに登場したり、現在も花笠踊りやかんこ踊り、太鼓踊りなどにその名残を残しています。
かぶき者というワード、そして流行歌にあわせて皆で踊る踊りというと、パラパラを思い出すのは私だけでしょうか。そこまで激しい踊りではないが手先の動きが多い点、そして単純な振付の繰り返しである点で、盆踊りはパラパラと似ています。もしかしたら、盆踊りと同じく風流踊りから発展したかぶき踊りにも、パラパラ的要素があったのかもしれません。
「夜」との親和性

小悪魔ageha 2020 SPRING
ギャル文化は2000年代半ばになると、色白でお姫様のような巻き髪をした「姫ギャル」を生み出します。そうした姫ギャルの一部はピンクやパープルカラー、蝶や薔薇などのモチーフを好み、従来のギャルの自己主張路線に、「夜」のエッセンスを加えていきます。
こうした姫ギャルスタイルは、多くのキャバ嬢から注目を浴びることに。「小悪魔ageha」「姉ageha」など、キャバ嬢をメインターゲットとした雑誌も創刊され、彼女たちの中で独自の進化を遂げました。キャバ嬢自体に憧れる女子も増え、この頃からさらにキャバ嬢人口が増えたといわれています。
一方のかぶき踊りは、評判になると今度は多くの女芸能者や遊女が真似をし始めました。遊女によるかぶき踊りのことを「遊女歌舞伎」と呼び、一度に踊る遊女は50~60人にも上りました。この遊女歌舞伎も大流行しましたが、風紀が乱れるとの理由で江戸時代になると幕府が禁止してしまいます。その結果、今日につながる男性のみが舞台に立つ歌舞伎に進化していくのです。
もちろんキャバ嬢と遊女は異なる職業ではあるものの、どちらも「夜」のイメージが強くないでしょうか。「ギャル」を支持したキャバ嬢と「かぶき踊り」を支持した遊女。ギャルと歌舞伎(かぶき踊り)は夜との親和性が高いという共通点があるのではないでしょうか。
ヘアメイクは違う自分になるためのスイッチ
平成時代にあれだけいたギャルたち。彼女たちは今もなおギャルなのでしょうか。
すでに彼女たちはアラフォー世代ですが、多くの人が就職したり結婚したりして、(多少のギャルっぽさはあれど)大人の女性になっているはずです。もちろんギャルメイクも卒業しているでしょう。つまり、ギャルにとってヘアメイクは、ギャルを最大限に表現するための一つのスイッチといえます。
同じことは、かぶき者にもいえます。かぶき者も生まれながらに「かぶいて」いるわけではありません。派手な着物をまとって茶筅髪にして、同じような格好の仲間がいてこそ「かぶけ」たのではないでしょうか。歌舞伎役者も同様です。たとえ歌舞伎役者であっても日常生活の中で「イヨーーーォ!」と見得を切ることはもちろんありません。
舞台の前に隈取してカツラをかぶり、初めて役に入るのです。彼らにとってもヘアメイクや衣装が違う自分になるスイッチであるのです。
舞台の上の人を見ている感覚

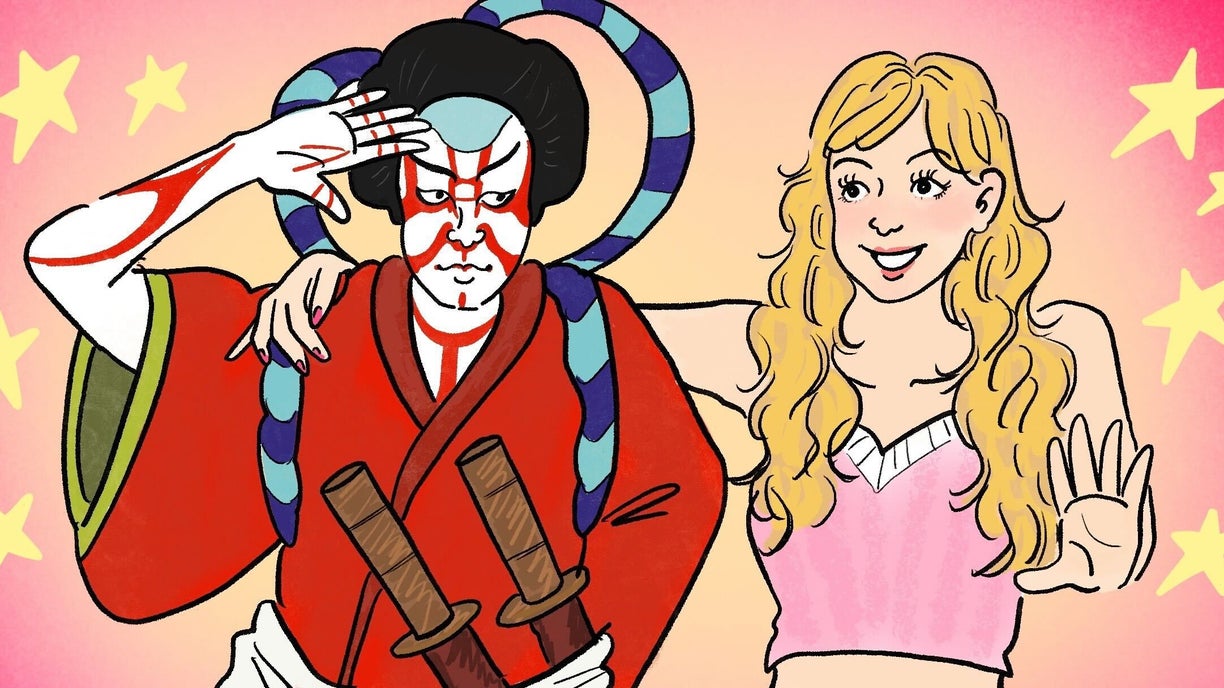
.jpg)
.jpg)