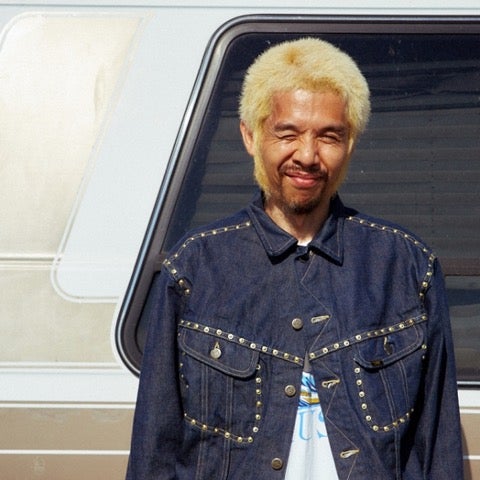もくじ
1.歌舞伎とは?
2.歌舞伎の歴史は江戸時代の初め頃までさかのぼる
3.歌舞伎の特徴的な表現方法
4.歌舞伎の人気・おすすめの演目
5.歌舞伎の代表的な屋号(家柄)と主な役者
6.歌舞伎を鑑賞するには?
まとめ.基本知識を身につけて歌舞伎の世界を楽しもう!
歌舞伎とは?
歌舞伎とは、「芝居」「踊り」「音楽」の3つの要素で成り立つ総合芸術です。そのレパートリーは数多く700以上にもなります。初めて歌舞伎を楽しむ人は、あらすじや歌舞伎独特の約束事などの解説を行ってくれる「同時解説イヤホンガイド(有料)」を使用するとよいでしょう。
花道の魅力を味わいたい場合、花道に近い1階席、舞台全体を鑑賞したい場合や宙乗りを楽しみたい場合は、2階や3階のチケットを取ることをおすすめします。
歌舞伎の歴史は江戸時代の初め頃までさかのぼる

歌舞伎というと伝統芸能として紹介されることが多く、古くから歴史があるイメージがあるでしょう。具体的にはいつ頃始まり、どのような歴史があるのかをご紹介します。
歌舞伎の始まり
歌舞伎の始まりは17世紀初頭、江戸時代の初め頃です。「出雲阿国」という女性が京都で始めた「かぶき踊り」が人気を集めました。その後、「かぶき踊り」を真似た女性芸能者の集団が次々と現れました。この女性たちによる踊りを「女歌舞伎」といい、当時の新しい楽器であった三味線も取り入れられて演じられるようになります。女歌舞伎の人気は高まり、京都だけでなく、江戸や大阪へ広まりました。しかし、女歌舞伎の人気があまりにも高まったため、ひいき同士の争いが起き、風紀を乱すとして禁止されることになります。
その結果、それまでも少年たちによって演じられていた「若衆歌舞伎」が人気を集めましたが、これもまた取り締まられ禁止となってしまいます。その後、少年ではなく成人した男性が演じる新たな歌舞伎として「野郎歌舞伎」が登場します。
歌舞伎の成立
17世紀後半~18世紀初め頃の江戸では、町人による文化や芸術が次々と誕生してきます。「野郎歌舞伎」は成人男性が演じますが、形式が作られていく過程で「女方(おんながた)」が生まれ、今日の歌舞伎の基礎ができあがりました。当時活躍していた歌舞伎役者の初代市川團十郎によって「荒事(あらごと)」が歌舞伎の表現様式として生まれたのもこの時期です。荒事は、荒々しく豪快な演技を指し、見得や六方などの演技様式が見られ、主人公は隈取りや誇張された衣装が特徴です。荒事は、その力強さやおおらかさなどが江戸の人々に好まれ江戸を中心に発展していきました。
一方、京都や大阪では洗練されたものが好まれ、柔らかく優美な表現技法「和事(わごと)」が生まれました。和事では落ちぶれた色男が馴染みの遊女を訪ねることで起こる出来事を優美に演じます。この和事では、初代坂田藤十郎が活躍しました。
歌舞伎の発展
19世紀前半になると、江戸では歌舞伎の新しい技法や演目が次々に登場します。かぶき踊りに始まった歌舞伎ですが、踊りとしての所作は声楽や三味線が流行することによって進展していきます。例えば、歌を軸とする「長唄」を伴奏として、「所作事(しょさごと)」や「振事(ふりごと)」と呼ばれる舞踏劇が形成されました。当初は女方の芸として形成されたものですが、所作事は立役によっても演じられるようになっていきます。
また、享保年間(1716~1736年)には、劇場も大きく変化し、屋根がなかった芝居小屋が屋根付きになりました。これにより、夜の演出がしやすくなったことで多彩なストーリーを上演できるようになりました。文政年間(1804~1830年)になると、娯楽を楽しむムードが社会に広がり、歌舞伎はいっそう人気を集めました。人々の生々しい生活を扱う「生世話物(きぜわもの)」という作風が誕生するとともに、「ケレン」という仕掛けを用いた亡霊や動物などが登場する演目も人気となりました。
この時代には後世に影響を与えるような名優が多く現れました。「実悪」を得意とした5代目松本幸四郎や愛嬌のある風貌で人気を集めた女方5代目岩井半四郎が活躍しています。そのほか、「音羽屋型」と呼ばれる演じ方を多く残した3代目尾上菊五郎、「色悪」を確立した7代目市川團十郎なども人気でした。
歌舞伎の近代化
19世紀の半ばになると、寄席で演じられる講談や落語などが人気となり、歌舞伎にも影響しました。この時代に活躍したのが4代目市川小團次です。名門の家系ではなく、容姿や声に恵まれていたわけでもありませんが、動きに優れ、踊りがうまく、実写的な演技やその演技で観客を泣かせることもあり人気を集めました。しかし、江戸時代末期になると歌舞伎に対する政府の弾圧が厳しくなります。
戊辰戦争によって幕府が崩壊し、明治時代になると「演劇改良運動」が起こります。外国に文明国である日本をアピールするために、近代社会にふさわしい内容に歌舞伎の内容を改めようと起こった運動で、明治20年には天皇による歌舞伎の観覧も実現し歌舞伎の地位が大きく向上することになりました。明治22年には「演劇改良会」の会員と金融業者の共同で「歌舞伎座」が設立されました。
現在の歌舞伎
歌舞伎は、江戸時代から活躍を続けた河竹黙阿弥のあと、作家がなかなか育たない時期が続きます。しかし、「演劇改良運動」によって文学者などが関わりやすくなったこともあり、明治時代後半から昭和初期にかけて坪内逍遙など外部の作者による作品が上演されるようになりました。これらの新しい作品は「新歌舞伎」と呼ばれ、2代目市川左團次によって盛んに上演されました。
東京歌舞伎では従来の歌舞伎も多く演じられ、5代目中村右衛門、6代目尾上梅幸、7代目松本幸四郎などが活躍しました。さらに、2005年にはユネスコにより、「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」として宣言され、2008年には「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載されました。
歌舞伎の特徴的な表現方法

歌舞伎には歌舞伎特有の表現方法が見られます。西洋のオペラなどの表現方法とは違うことが想像できますが、同じ日本の能楽などとも違う特徴的な表現方法があるので、どのようなものがあるのかをご紹介します。
歌舞伎の主な演出
歌舞伎の表現方法には主に以下のような演出があります。
【引抜】
衣装を舞台上で一瞬にして変える演出の一つで、仕付け糸で留められた2つの衣装を重ねて着込み、舞台上で仕付け糸を抜き取り、上に着込んだ衣装を取ることで下の衣装が現れる仕組みです。主に舞踊で行われ、観客の目先を変える演出として用いられます。
【宙乗り】
幽霊や妖怪、人間に化ける狐など、現実にはいないような役において、俳優が舞台や客席の上を吊られて移動する演出です。
【立廻り】
立廻りは、斬り合いや格闘の場面で行われる際の様式的な動きのことです。1対1の場合もあるものの、大勢の軍兵や捕り手を演じる脇役が主役に向かって挑みかかる場合が多いです。「下座音楽」に合わせて演じられ、主役は「見得」を要所で行います。
【六方】
主に「荒事」の役が「花道」を引き込むときに演じられる、手足の動きを誇張して、歩いたり走ったりする様子を象徴的に表現した演出です。この演出によって、観客には力強さと荒々しさが強く印象づけられます。
【見得】
感情の高まりなどを表現するため、演技の途中で一瞬ポーズをつくって静止する演技をする演出となります。「立役」を中心に行われ、人物をクローズアップさせる効果があります。
【人形振り】
「義太夫狂言」という人形浄瑠璃から歌舞伎に移された演目で、俳優が人形の動きをまねて演じる演出のことです。
【黒衣】
舞台上で俳優の補助をする役割を「後見」が、顔を隠して全身黒い衣装を身につけている姿を「黒衣(くろご)」といいます。歌舞伎では黒は見えないというルールなので黒衣も舞台上では見えないことになっています。
情景を表す演出
歌舞伎は以下のような演出で情景を表します。
【舞台装置による演出】
ミュージカルをはじめとした現代の舞台では立体的な舞台装置が用いられることがほとんどですが、歌舞伎においては配置されたときの美しさを重視して平面的な絵のように構成されることが通例になっています。風景は「書割(かきわり)」、建物は「屋台(やたい)」といった大道具を用います。また、幕も舞台装置として用いられ演出の手助けをします。
【天候を表す演出】
季節や天候を表す演出には、舞台装置だけでなく小道具や大道具、効果音、そして音楽を効果的に使用します。例えば、雪は小さく切った白い紙を散らす、地面や床を表すために舞台に「地絣(じがすり)」を敷くなどです。効果音などは現実ではない雪の降る音を表す「雪音(ゆきおと)」など歌舞伎特有の効果音があります。
【松羽目物の演出】
能や狂言を歌舞伎化したものを「松羽目物(まつばめもの)」と呼びます。「松羽目」は舞台正面の大道具として使用する松が描かれた羽目板のことです。松羽目以外にも、衣装やせりふにも能や狂言の表現を用いた演出が見られます。
【幕切の演出】
歌舞伎では、ある場面が終わるときに幕が引かれることが通例となっており、これを「幕切れ(まくぎれ)」と呼びます。幕切れの演出には、舞台全体を絵のように均整の取れた構図にする「絵面(えめん)の見得」、「三段」と呼ばれる緋毛氈に包まれた階段を使用した幕切れ、幕が引かれたあとに「花道」を利用して余韻を持たせながら退場する「幕外の引込み」などの演出方法があります。
音による演出
歌舞伎に用いられる音による演出には以下のようなものがあります。
【下座】
歌舞伎の舞台下手には「黒御簾(くりみす)」という音楽を演奏する場所があり、ここで演奏されるものを「下座」もしくは「下座音楽」と呼びます。
【鳴者】
歌舞伎に用いられる音楽では三味線以外の楽器全般や演奏を「鳴物」と呼びます。舞台上で長唄の「唄方」と「三味線方」と一緒に演奏する場合は「出囃子」と呼ばれます。
【長唄】
三味線音楽の一つで、「歌いもの」に分類される歌舞伎舞踊の伴奏音楽です。歌舞伎の音の表現において大きな役割を担っており、唄方と三味線方で下座音楽の多くを担当しています。
【竹本】
歌舞伎において語りの担当である「太夫(たゆう)」と三味線方から構成される、「義太夫節(ぎだゆうぶし)」とその演奏方を指すのが竹本です。主に人形浄瑠璃を歌舞伎に移した「義太夫狂言」で用いられます。
【常磐津節】
「常磐津」とも呼ばれており、物語を節で語る「浄瑠璃」の一つです。歌舞伎においては観客から見える舞台上で演奏され、主に舞踊の伴奏として用いられます。曲調はゆったりとして重厚な雰囲気があります。
【清元節】
浄瑠璃の一つで、「清元」とも呼ばれています。舞踊の伴奏として用いられるほか、劇中の演奏会や稽古という設定で舞台上で演奏します。高い音域で技巧的に語るのが特徴です。
【柝】
2本の四角い拍子木を打ち合わせて音を出し、楽器と楽器から出される音の両方を柝(き)と呼びます。効果音として用いられるほか、演技のきっかけを作る、俳優に時刻を知らせるなどの役割があります。
【ツケ】
「ツケ板」と呼ばれる板が舞台上手に置かれており、それに四角柱の木を打ち付けて出される音を「ツケ」といいます。動作や物音を強調する効果があります。
歌舞伎の人気・おすすめの演目

歌舞伎には人気の演目が多くあります。ここでは、おすすめの演目をいくつかご紹介します。
助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)
吉原で出会う男に片っ端から喧嘩をふっかけては相手に刀を抜かせていた江戸一番の伊達男六助(曽我五郎時致)と、その恋人で吉原一の花魁・揚巻。揚巻を自分のものにしたい権力者のひげの意休は、助六に挑発されても刀を抜きませんでした。そもそも助六は源氏の宝刀・友切丸を探すために吉原に出入りしていたのですが、意休がこの刀を持っていると聞き出し、奪い返すというストーリー。
歌舞伎の演目のなかでも華やかさに長けた作品です。花魁の衣装は美しく、特に「揚巻」の衣装の豪華さには目を奪われてしまいます。また、登場人物も多彩で助六の兄や母、意休の子分・くわんぺら門兵衛、朝顔仙平などさまざまです。2時間近い舞台も飽きずに楽しめるでしょう。
勧進帳(かんじんちょう)
源義経、弁慶の一行が、山伏に扮して奥州平泉へと落ち延びていく際、安宅の関を通過するときの攻防を描いた作品です。義経を捕らえる命を受けている関守・富樫左衛門は一行を疑い、山伏が持っているはずの勧進帳を見せるようにと執拗に詮議します。弁慶は何も書いていない巻物を勧進帳であるかのように読んでごまかし、「お前のせいで疑われた」と荷物持ちに扮した義経を杖で打ち据えます。荷物持ちが義経であると気付いていた富樫は、弁慶の忠義心に打たれて関所の通過を許します。
「荒事」を中心に作られた「歌舞伎十八番」の一つで、高い人気を誇り上演回数も多い名作です。息詰まる「山伏問答」や弁慶による「延年の舞」「飛び六方」での引っ込みなど見所は多くあります。弁慶の忠義心の強さには胸が熱くなりますが、情に厚い富樫の演技も必見です。
暫(しばらく)
「しばらく」という大きな声が印象的な「暫」は、東京オリンピック2020開会式で市川海老蔵(現市川團十郎白猿)が演じたことで記憶にある方もいるでしょう。
大悪人清原武衡がたくさんの手下を引き連れ、鶴岡八幡宮の前で通りかかったカップルに嫌がらせをしていると、「しばらく」という大音声とともに、鎌倉権五郎が派手で巨大な衣装に身を包み登場します。権五郎は困っているカップルを助け、武衡の手下たちの首を一刀のもとにはね、悪を成敗した権五郎が堂々と花道を引きあげていくというストーリーです。
暫もまた歌舞伎十八番の一つで、團十郎家のお家芸ともいえる演目となっています。
東海道四谷怪談(とうかいどうよつやかいだん)
四谷左門の娘、お岩とお袖の姉妹を巡る怪談劇で通称「四谷怪談」と呼ばれるものです。お岩の夫・民谷伊右衛門を孫娘の婿に迎えたい伊藤喜兵衛がお岩に毒を飲ませ、お岩の面相が変わってしまいます。醜いお岩を見た伊右衛門はお岩を捨てようとし、それを知ったお岩は恨みを残したまま死んでいきます。その後、お岩は幽霊となり、伊右衛門をはじめ伊右衛門の母や仲間を次々と巻き込み凄惨な復讐劇を繰り広げていきます。最終的に伊右衛門はお袖の夫である佐藤与茂七によって打たれてしまいます。
お岩の夫である伊右衛門は二枚目の色男ですが、極悪非道な行いをする、歌舞伎では代表的な「色悪」として知られる役です。怪談物であるため、幽霊となったお岩の表現には「ケレン」が演出として次々と登場します。また、毒を飲まされたお岩が櫛で髪を梳き、髪が抜け落ちて顔が醜く崩れていく壮絶な場面では「下座音楽」でお岩の恨みや悲しみを表現しており、作品最大の見所となっています。
義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)
全5段からなる演目で、平家滅亡後に兄の頼朝と不和になった源義経を軸として描かれる、平家の生き残った人々の動向を描いた「時代物」の「義太夫狂言」となっています。
壇ノ浦で入水した平知盛が実は生きていて、義経への復讐を企てる「渡海屋」・「大物の浦」、「すし屋」では平維盛親子を守るために命を落としたいがみの権太を描き、源九郎狐が佐藤忠信に化け、義経から両親にゆかりの初音の鼓を授かる「河連法眼館」(通称・四の切)といった場面が上演されます。
「義太夫狂言」でよく見られる演出の一つに「もどり」というものがあります。これは、悪人として登場した人物が、後に善人であったことを明らかにする演出です。「すし屋」の権太がこれにあたります。また、5段のなかでも人気がある「大物の浦」のラストには、「碇知盛」と呼ばれる、血まみれの知盛が巨大な錨を持ち上げて海に後ろ向きに飛び込んで自害する壮絶な場面があり、大迫力の見せ場となっています。
菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)
全5段からなり、平安時代の貴族菅原道真が陰謀により左遷された事件を題材にした「時代物」の「義太夫狂言」です。
菅原道真が津罪となった際に、伯母と娘と別れるときの奇跡を描いた「道明寺」。梅王丸、桜丸、松王丸の三つ子の兄弟が、敵味方に分かれて争う「車引」、道真が流罪となるきっかけを作った後悔から桜丸が切腹をする「賀の祝」、道真の子ども管秀才を救うために松王丸が自らの子を犠牲にする「寺子屋」などを中心に上演されます。
全5段のなかで特に人気が高いのは「寺子屋」で上演回数も多くあります。「せまじきものは宮仕えじゃなあ」という現像の苦悩を表す名台詞が有名です。首桶を開けて確かめる瞬間の、緊張の瞬間は見せ場の一つです。
仮名手本忠臣蔵(かなでほんちゅうしんぐら)
元禄時代に起こった赤穂浪士による仇討ちが題材となった「時代物」の「義太夫狂言」で、上演回数が一番多い人気作です。設定は南北朝時代の太平記に移しており、登場人物の名前も太平記の人物に置き換えられています。そのため、大石内蔵助は大星由良之助という役名になります。
物語は全11段で、高師直(吉良上野介)が塩冶判官(浅野内匠頭)の妻である顔世御前に横恋慕するところから、由良之助(大石内蔵助)以下四十七士が討ち入りを遂げるまでが描かれています。
「大序(だいじょ)」という冒頭部分が「時代物」の序段にありますが、現在では「仮名手本忠臣蔵」にのみ「大序」の演出が伝わっています。「とーざいー」とくり返される声や、「柝」がゆっくり打たれるのに合わせて「定式幕」が徐々に開けられ、人形のように伏せた登場人物が現れるなど、儀式化され厳かな雰囲気がある「大序」の演出は見せ場の一つです。
京鹿子娘道成寺(きょうがのこむすめどうじょうじ)
白拍子の花子が道成寺の鐘供養に訪れ、舞を次々に披露します。次第に花子の様子が変わっていき、最後には鐘のなかに飛び込み、恐ろしい顔の蛇の姿になって現れるというストーリーです。
「娘道成寺」や「道成寺」と略されることもある京鹿子娘道成寺ですが、能の「道成寺」から鐘供養に訪れた女性が舞を披露し、恨みの表情で鐘に飛び込むというストーリーを取り入れています。一時間近くを女方が踊りぬく作品で、さまざまな女心を踊りわける女方憧れの演目です。義太夫による音曲の聞かせどころ「クドキ」や、舞台上で一瞬にして衣装を変える「引抜」など見所が多数あります。
恋飛脚大和往来・封印切(こいびきゃくやまとおうらいふういんきり)
飛脚問屋の若旦那忠兵衛は馴染みの遊女梅川を身請けしようとしますが、お金が足りません。同じく梅川を身請けしようとしていた丹波屋八右衛門は、梅川の必至の哀願によって忠兵衛を優先させることにした梅川の抱え主槌屋治右衛門に断られます。腹立ち紛れに忠兵衛を罵り挑発し、言い争いになります。その際、忠兵衛が懐から取り出した公金の封印が切れてしまい、忠兵衛はそのまま公金に手をつけ梅川の身請け金の残りを払ってしまいます。晴れて梅川を身請けでき、祝福される忠兵衛ですが、梅川と二人きりになると事情を打ち明けます。自分たちの弔いの費用をおえんに渡すと忠兵衛は梅川と心中してしまいます。
この演目の最大の見せ場は、忠兵衛が封印を切る場面です。直後に演奏される「竹本」の速いテンポの三味線によって、忠兵衛の後悔の念が表現されています。
紅葉狩(もみじがり)
能の作品から歌舞伎化された作品で、平維茂による信州の戸隠山の鬼女退治を描いた同名の作品が元になっています。
平維茂は戸隠山へ紅葉狩りに行くと、更科姫という姫に出会います。姫にすすめられ酒を飲むと、やがて姫は鬼女の正体をあらわし、酔い潰れた平維茂に襲いかかります。しかし、平維茂は名刀小烏丸によって難を逃れます。
「竹本」、「長唄」、「常磐津」の3つの「音曲」によって伴奏される舞踊の作品で、2枚の扇を使用する更科姫の踊りは見所の一つとなっています。
歌舞伎の代表的な屋号(家柄)と主な役者

歌舞伎は親から子、師匠から弟子へ受け継がれることが多く、役者の家系(屋号)によって芸の特徴も異なります。ここでは、代表的な屋号と主な役者をご紹介します。
成田屋(なりたや)
成田屋は、歌舞伎界の宗家と呼ばれる市川團十郎家だけの屋号です。初代市川團十郎に始まり、家紋は三升となっています。成田屋という屋号は、初代團十郎が跡継ぎに恵まれず、成田山新勝寺に祈願したところ男の子が生まれたことが由来です。
成田屋は歌舞伎で最初につけられた屋号で、これにならい他の家も屋号をつけるようになりました。荒々しい演技が特徴の荒事を創始したのも初代團十郎で、後に七代目團十郎が「歌舞伎十八番」を制定し、他の家も対抗するようにそれぞれのお家芸を選定するようになりました。歌舞伎には見得がありますが、成田屋というと「にらみ」が有名です。「にらみ」は祝賀として行われ、片目は寄り目、もう片方の瞳は目の中心にするという特殊な目の動きをします。成田屋の「にらみ」は邪気を払うという意味が込められており、見た人は一年風邪を引かないと言われています。
音羽屋(おとわや)
音羽屋は、京都で「都万太夫座」の観客案内や飲食提供のような仕事をしていた頃から始まりました。初代尾上菊五郎の父親が、生誕地にほど近い清水寺の「音羽の滝」にちなみ音羽屋半平を名乗っていたことが由来です。音羽屋は五代目尾上菊五郎から、尾上菊五郎家、尾上松禄家、板東彦三朗家に家系が分かれています。なかでも尾上菊五郎家は歌舞伎界屈指の名門の一つとなっており、五代目菊五郎と九代目團十郎は同じ時代に活躍したことで、「團菊」と呼ばれていました。
音羽屋は女方、立役の両方を演じる一門で、「兼ねる役者」であることが伝統的に受け継がれています。
中村屋(なかむらや)
中村屋の大名跡といえば18代まで続く「中村勘三郎」です。この名跡は、江戸時代に興業が許された三座の一つである「中村座」の座元に受け継がれているものでした。しかし、幕末からは長い期間名乗る役者がおらず、復活させたのが一七代目勘三郎で昭和25年のことでした。名跡の復活以来、現在の中村屋の屋号が始まりました。家紋は「角切銀杏」となっています。
戦後の歌舞伎界を支えた一七代目勘三郎は、800種類もの役を演じギネスブックに登録されています。その名跡を継いだ一八代目中村勘三郎は、古典歌舞伎の演目を若者向けに渋谷コクーン劇場で演出を新たにして上演する「コクーン歌舞伎」や江戸の芝居小屋を再現した「平成中村座」での国内外公演など、新たなことに挑戦し続け歌舞伎界の発展に尽くしました。
高麗屋(こうらいや)
初代松本幸四郎が神田の高麗屋で丁稚奉公をしていたことが由来となっており、四代目幸四郎から「高麗屋」の屋号を使用しています。高麗屋の家紋は「四つ花菱」です。
一時期高麗屋を継ぐ家系が断絶してしまいますが、九代目市川團十郎の弟子から七代目松本幸四郎が復活し、現在の松本幸四郎家となっています。そのため、團十郎譲りの荒事を得意芸としており、なかでも「勧進帳」の弁慶役を得意としています。七代目幸四郎はこの弁慶役を生涯に1600回演じているため、本家團十郎家以上のお家芸といえるでしょう。
播磨屋(はりまや)
初代中村歌六が播摩谷作兵衛の容姿に出されたことから、「播磨屋」の屋号がつけられました。播磨屋には中村吉右衛門家と中村歌六家があり、吉右衛門家の家紋は「揚羽蝶」、歌六家の家紋は「桐蝶」となっています。
松嶋屋(まつしまや)
松嶋屋の大名跡には「片岡仁左衛門」があり、上方歌舞伎の名門として有名です。終戦後に関西では劇場が減っていったため、消滅の危機に陥った上方歌舞伎ですが、一三代目片岡仁左衛門が私費を投じて自主公演を開催し、それをきっかけに芝居が再興していきました。家紋は「七つ割に二引」で、屋号の「松嶋屋」の由来は良くわかっていないそうです。
成駒屋(なりこまや)
「成駒屋」の屋号は、四代目市川團十郎が四代目中村歌右衛門に「成駒柄の着物」を贈ったことが由来となっています。もともと立役の家系だった成駒屋ですが、五代目中村歌右衛門によって女方の名門として知られるようになりました。特に戦後を代表する名優である六代目中村歌右衛門は、女方の最高峰としてその名を馳せました。成駒屋の家紋は「祇園守」となっています。
大和屋(やまとや)
初代坂東三津五郎を養子とした初代坂東三八の実家の屋号が由来となっている「大和屋」。江戸時代に森田座の座元と役者を兼ねていた守田勘弥家ですが、十二代目守田勘弥の頃に新富座と名前を変え、子どもの代からは役者に専念しています。守田勘弥家は今の坂東三津五郎家と坂東秀調家とつながり、この産気は一門としてつながりがあります。家紋は「三つ大」です。
大和屋からは舞踊の名手が数多く輩出されており、個性的で芸達者な役者が多い特徴があります。現代では女方の名役者、五代目坂東玉三郎が有名ではないでしょうか。
澤瀉屋(おもだかや)
澤瀉屋のオモダカという言葉を聞き慣れない方もいると思いますが、これは薬草の種類のことです。初代市川猿之助の生家が薬屋だったため「澤瀉屋」という屋号になり、家紋も薬草のオモダカをあしらった「八重澤瀉」となっています。
澤瀉屋は新しいことに挑戦する特徴があり、特に三代目市川猿之助(現二代目市川猿翁)によって創設されたスーパー歌舞伎が有名です。現代言葉での台詞が多く、派手な最新技術を用いた演出であるため、歌舞伎を知らない若い世代でも見やすくファンを増やしました。四代目市川猿之助も、古典歌舞伎をこなしながら、人気漫画を題材としたスーパー歌舞伎Ⅱ(セカンド)を上演し若いファンを増やしました。
萬屋(よろづや)
屋号「萬屋」は、三代目中村歌六の妻の実家が経営していた芝居茶屋の名前が由来となっています。養子を取り、後を継がせることも珍しくない歌舞伎の世界ですが、中村時蔵家は実施の血統で続く珍しい家系です。家紋は「桐蝶」となっています。
現在は五代目中村時蔵を筆頭に、二代目中村錦之助やその息子である中村梅枝、初代中村隼人など若手の人気俳優を輩出しています。テレビドラマや映画で目にすることが多い中村獅童も萬屋の家系に名を連ねています。
山城屋(やましろや)
山城屋の大名跡「坂田藤十郎」は長らく空いていましたが、2005年に三代目中村雁治郎が四代目坂田藤十郎として復活させました。なぜ屋号が山城屋となったのかその由来ははっきりしません。家紋は「五つ藤重ね星梅鉢」です。
上方歌舞伎伝統の柔らかみのある和事を継承した四代目藤十郎ですが、江戸時代に藤十郎と組んで一時代を築いた近松門左衛門の全作品上演を目指し近松座というものを結成しています。
歌舞伎を鑑賞するには?

歌舞伎に興味を持ってもどのように鑑賞したら良いのかわからない方もいるでしょう。ここでは、歌舞伎を鑑賞できる場所やマナーをご紹介します。
歌舞伎を鑑賞できる場所
歌舞伎鑑賞といえば東京の歌舞伎座を真っ先に思い浮かべる方も多いでしょう。東京都内では、歌舞伎座と国立劇場ではほぼ定期的に歌舞伎の公演があります。それ以外にも、新橋演舞場や大阪松竹座、京都四條南座、名古屋御園座、博多座などでも鑑賞できます。また、地方の劇場でも公演が行われる場合があるので、お住まいの地域の文化会館や劇場の情報をチェックするのもおすすめです。
チケットは松竹のWebサイトや電話、劇調の窓口、チケット販売サイトなどで入手できます。
歌舞伎を鑑賞する際のマナー
伝統芸能の代表格ともいえる歌舞伎ですが、観劇の際に着物などのフォーマルな服装をしなくてはならないと考える方もいるでしょう。しかし、実際は特別なドレスコードなどはなく、カジュアルなスタイルでの観劇でもかまいません。歌舞伎の公演は長時間である場合が多いので、楽に観劇できるスタイルにするのがおすすめです。
歌舞伎座などの歌舞伎の劇場では座席での食事ができるため、お弁当の持ち込みが可能です。そのほか、公演中は携帯電話の電源を切る、撮影や録音は禁止などの歌舞伎以外でも遵守する必要がある基本的なマナーは守りましょう。
基本知識を身につけて歌舞伎の世界を楽しもう!

歌舞伎を初めて観に行くなら、歴史や表現方法、演目のあらすじ、代表的な役者などを知っていると、より楽しめるでしょう。不安な場合でも字幕や音声ガイドがある公演もあるので安心して観劇に行ってください。また、鑑賞する際のマナーも知っておくと、当日落ち着いて鑑賞できるでしょう。
私たち5PM journalは、熱量を帯びている偏愛に解釈を添えて、「あらたな気づき」を生み出すことを掲げて運営しているメディアです。ぜひ、その他の記事もご覧になってみてください。
【参考URL】
はじまり | 歌舞伎の歴史 | ユネスコ無形文化遺産 歌舞伎への誘い
歌舞伎の誕生から現在まで、鑑賞前に知っておきたい歌舞伎の歴史 - OZmall
歌舞伎の演目で有名なものを紹介!初心者におすすめの12作品を解説 | 歌舞伎の達人
歌舞伎役者の屋号一覧はこれ!有名な屋号の由来と代表役者の子供も紹介 | 歌舞伎の達人
【東京】歌舞伎を鑑賞できる劇場は?歌舞伎座・国立劇場・浅草公会堂ほか - おすすめ旅行を探すならトラベルブック(TravelBook)